江戸時代に伊丹で栄えた酒文化
江戸時代に伊丹の酒文化は大きく栄えました。
国文学者であり伊丹町長・市長を務めた岡田利兵衛氏の「徳川中葉の伊丹酒」に詳しく書かれています。この書の冒頭に、そもそも「伊丹酒」という言葉が野暮であるという記述があります。
つまり、当時は伊丹といえば酒の代名詞であったというくらい、伊丹の酒は全国で有名であったということです。
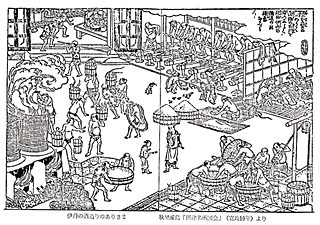
秋里離島「摂津名所図会」(寛政10年)より

(伊丹武内利兵衛氏所蔵)より
清酒酒造業の起源については諸説ありますが、発祥地は北摂であり、江戸時代に発展したことは確かです。醸造業は寛永から慶安に入って伊丹で盛大に行われました。
そして近衛家が伊丹の領主となると、醸造業はますます活気を増していきました。近衛家が伊丹酒に特別の庇護を加えたからです。伊丹で造られた酒は、「近衛殿御家領摂州川辺郡伊丹郷」の旗印を堂々とかざして、江戸に京都にと、全国へ流通しました。五摂家の随一であった近衛家の名を受けて、伊丹酒は他のどこの酒よりも優先権を与えられていました。
「売れる、売れる、酒さえ造っておれば黄金が湧いて蔵が殖えた」というくらいのものだったのです。
これらの酒は、伊丹から高瀬舟に載せられて、猪名川から神崎の浜へ、そして海路で江戸へ送られていました。
この頃の記録には伊丹の酒屋として、68の酒屋の名前が並んでいます。
これらの酒屋の主人は、風流なものを理解し愛する人が多く、例えば「油屋」の上嶋鬼貫などを始めとして、俳諧を嗜む人がたくさんいました。更に一文字屋与治兵衛が俳人好昌であり、新町丸屋仁兵衛が鷺助であるなど、高名な俳人は枚挙にいとまがありません。
酒と共に花開いた文化の数々
各酒造家はそれぞれ自家独特の酒銘を持っていました。それも一つや二つでなく、次第に増加していきます。それを酒樽を包む菰巻の外に大きく記入して(酒印または菰印とも呼びます)店や得意先に送りました。たくさんの印を用意していたのは、得意先によって印を変えたり、製造法によって区別したりすることもあったためと考えられています。
この酒銘にはいわゆる商標権利があったので模造したり、勝手に使用したりすることは出来ませんでした。即ち始めて作ったり借用したり相続したり売買したりする時は、その都度届け出たものと思われます。
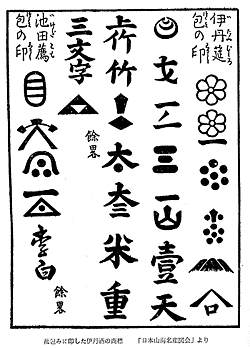
「日本山海名産図会」より
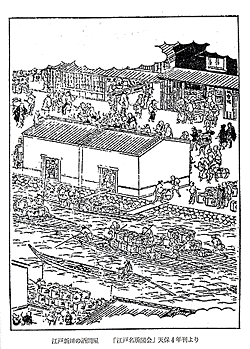
天保4年刊より
旧伊丹酒造組合所蔵の印帳は、酒銘の所謂登記簿のようなもので、近年の幕末頃のものまで記入されていますが、この中にある鹿島や茂兵衛の商標は 白鹿
等が載っています。(鹿島や清太郎と茂兵衛は同一家です)
大きくまた、この印帳の初めの方に載っているのは古いもので正徳の油屋の顔ぶれが見えます。例えば八尾八左衛門は紙屋八左衛門であり、小西新右衛門は薬屋新右衛門、上嶋八郎兵衛は油屋八郎兵衛、柄谷庄右衛門は植松庄右衛門です。紙屋八左衛門の菊印は彼の松江維舟の句「伊丹こそ菊の元船江戸廻し」に読まれているところで、最も古いもののひとつとして有名です。
また、薬屋の 、白雪、庄右衛門の
、油屋の三文字なども古くから知られています。なお、この印帖によると、上述の鹿清の白鹿を始め山本庄兵衛の男山、大関等現今灘方面に使用されている酒印が少なからず含まれています。これらはその印が当地の酒に本源を持った証です。
この頃の伊丹酒の品質はどうだったかと言うと、言うまでもなく天下の絶品でした。伊丹酒がよく売れた原因は、近衛家の特別の庇護によるものでもありますが、それだけではありません。品質が芳醇で他と比べるものがないくらい当時の愛飲家を魅了したというところも大きかったのです。
天からの恵みである、伊丹の井戸水が使われていましたが、中には東を流れる猪名川の水を汲んで酒に用いたこともあったようです。(これは池田郷でもっぱら行われていたようです)
この特殊製造で造られた酒にはの焼印を用いていました。(焼印とは、菰巻の酒印の肩に焼いて捺した印をいいます)
また、一文字屋では箕面山頭の滝水を使用して酒を醸し、その銘を滝水といったと逸士伝は記しています。それからという焼印をも捺したのものもあります。これは米を吟味したことを表現するもので、三嶋郡粟生村の産米を用いるということです。粟生村は現在に至るまで米産地として知られています。
そしてこの頃の伊丹酒がどれくらいの価格で江戸へ売られていたかというと、有岡年代秘記正徳五年の条を見ると、「伊丹酒江戸売口五十二両」とあります。これはその頃の物価としては余程高価であったと思われます。
さらに灘酒沿革誌の江戸積の市価を見ると、
| 伊丹酒 | 三六両三歩 |
| 池田酒 | 三四両一歩 |
| 西宮酒 | 三三両二歩 |
| 堺酒 | 三三両三歩 |
| 御影西組酒 | 三五両 |
とあって、伊丹酒は断然トップを切っており、他の追従を許していません。
これらを見ても、伊丹酒の品質が他の産地のものより群を抜いてよかったことが窺い知られます。
井原西鶴は『西鶴織留本朝町人鑑』の「津の国のかくれ里」に次のように述べています。
「爰に津の国伊丹諸白を作りはじめて家久しく……池田、伊丹の売酒、水より改め米の吟味、麹を惜まずさはりのある女は蔵に入れず、男も替草履はきて出し入れすれば、軒をならべて今の繁昌、枡屋、丸屋、油屋、山本屋……」
よく当時の実状を示しており、その頃の酒家がいかに米、水を吟味し細かいところまで注意して吟醸したかを物語っています。
この枡屋は上記酒屋名寄せ中の枡屋九郎左衛門(鹿嶋家)であり、丸屋は丸屋甚兵衛(森本家)、油屋は油屋八郎兵衛、山本屋は池田の山本屋太郎右衛門を指しています。
徳川中葉の伊丹の町は、時にとっての文士芸術家達の隠れ里でした。俳人であれ、詩人であれ、小説家であれ、伊丹酒の芳香は彼等の心をとらえ蕩かすにあまりにも適していました。
中でも、頼山陽が竹田、小竹等と常に伊丹に出没滞留して、時の銘酒剣菱の美に蕩酔し、
兵可用、酒可飲
海内何州当此品
屠販豪侠堕地異
(中略)
伊丹剣菱美如何 伊丹剣菱の美は如何(いかん)
各酹一杯能飲麼
と歌っている「戯作摂州歌」は有名です。
また、当時の伊丹酒造家の生活は、大名も一目置くほどの豪奢ぶりでした。その様子は、前掲の「織留」の津の国のかくれ里の節に西鶴が詳細かつ巧みに描いています。
そしてまた酒屋の力は実に偉大なるものでした。元祿十年十月には酒家年中行司へ惣宿老の称号を仰つかっています。
酒の都、伊丹
時代は少し後になりますが、享和元年8月調べの伊丹の軒数は2167軒で人口8237人となっています。江戸時代中頃も、多くて2000軒余の家数と1万近くの人口だったのではないでしょうか。そのうちで100軒の酒屋があり、それに附随した出入商人、十万石近くの米を動かす米屋、年二十万丁からの樽を製造する樽屋、それから竹屋、薪屋、菰屋、運搬問屋や諸職人までを加えると、町の大部分は酒で占められ、まさに酒の都であったことが想像されます。
寒造りの最中、伊丹高台から四方の溝渠に向かって流れ落ちる水は、白く濁っていました。これは米を洗う汁の流れであり、周りの田畑からはこの肥料によってたくさんの米が収穫できました。
また、袋洗いと言って毎酒造期の終りには酒袋を洗浄しますが、この水は白いだけではなく鼻を衝くほど芳醇な香りがします。これはアルコール分を多量に含有しているためで、粕汁よりは、この水のほうがが余程酔えたと言われています。
賤の女や袋洗の水の色 鬼貫
この鬼貫の句は酒の街・伊丹の当時の様子を生き生きと伝えています。
